行き詰まったとき、本にその答えを求めようとします。壁の向こうには何かあるのですね。
最近、読んだ本で感銘を受けた本を紹介しましょう。
天外伺郎 著“非常識経営の夜明け”というタイトルいの本である。
天外さんは、ソニーでCD,ロボット犬“アイボ”を開発した立役者である。
今経済は、かつて体験したことのない危険な領域に入ってしまっています。高学歴の人々がITを駆使し、高度な経済工学理論に基づいた取引を行っていてもこの事態は起きてしまいました。
彼の本には、右上の図が載っています。経済学は後追いでしかないという。
先を走る人は、現場のドロドロした中にタオを発見し「こうやればうまくいきそうだぞ!」という手法を実践に移す(古い脳を活性化させる)。それが、ひらめきであり、直感である。しかし、経営学者は成功者の複数の共通点を抽出し、体系化する(新しい脳を活性化させる)。その中にはタオの痕跡はあるが生々しいタオは肌では感じていない。そして、現在多くの企業が新皮質的な経営をしていることを指摘している。
では、どうしたらいいか?彼は言う。
「燃える集団」作りをすることである。チームが誰にもコントロールされずに、自立的に進むべき方向を決定できる状態にあること。部下を徹底的に受容し、信頼し、自律的な動きにまかせて指示・命令をしないマネジメントスタイルを「長老型マネジメント」と呼んでいる。人間なら誰しも潜在的に持っている、すさまじい能力を引き出し、活用するのである。このような状況下の精神状態のことを「フロー」と彼は呼ぶ。
そして、彼はさらにその理想を以下のように考えている。
1.企業経営の最も大切なことは、まず自分が楽しいこと。次に仲間やお客さんが楽しいこと。人を喜ばせること。本質的に楽しいことだ。
2.意味のない自己満足や優越感、上辺だけのかっこつけ、虚栄心、業界の評判などの見せ掛けの表面的な楽しさと、心の本当の楽しさを混同しないこと。
3.「ちょっとアホ!」に徹して遊び心、いたずら魂を発揮することが大切。
4.「正しいか、正しくないか」「良いかわるいか」「~するべきか、~しないべきか」などの常識的な基準は「ちょっとアホ!」の天敵。
5.自ら賢明に努力し、反省し、根性を持って頑張り、他にもそれを強要することは最悪。いい結果は生まれない。
6.和気あいあいとダラダラ仕事をやったのでは本物の楽しさは得られない。知恵を出し切り、工夫しまくりどんなアホなことでも徹底的に没頭してやりきる。
7.自分に対しても、上司や部下に対しても、お客さんに対しても「正直」であること。
8.社員に理念を徹底しなければいけない。わかりやすく簡単なことばで繰り返し。
9.会社の本当の成長は、規模が大きくなることではない。仲間が楽しく、お客さんが楽しく、会社に関係する人々がより楽しく、なるような会社にすることだ。
10.会社にとって最も大切なことは、社員一人一人の人間的成長。
11.社員の採用基準は、まず「いい奴」かどうか、次に「やってやるで」と思っているかどうか、最後に能力である。
12.「現状分析して、問題を見つけ出し、反省し、解決へ向かう」という従来の仕事の進め方は、あら捜しをして文句をつける拷問を誘う。「楽しくないから反省は一切禁止」「予算管理や目標進捗状況の把握はゲーム感覚で」
13.精密な計数管理をし、詳しく分析して現状把握したところで、やたら忙しくなるばかりで、売り上げが増えるわけではない。むしろ経理処理は徹底的に手を抜いて、昔ながらの「どんぶり勘定」戻せば、社員は暇になり楽しいことを企画するようになる。そのほうが売り上げが上がる。
14.倒産の危機や病気は「気づき」へつながるありがたい出来事だ。
15.学ぶ作業は、知り、納得し、行動し、他人に影響を与えてようやく完結する。
私が組織を纏める方法の、指針としていきたいと思える示唆を多く提供して貰い、一筋の光明が見えた思いのする書物であった。
天外氏の講演会に出られた、現日本サッカー 代表監督の岡田氏のコメントも載せられており、サッカーのチームを創る上でも実践して見たい。
最近、読んだ本で感銘を受けた本を紹介しましょう。
天外伺郎 著“非常識経営の夜明け”というタイトルいの本である。
天外さんは、ソニーでCD,ロボット犬“アイボ”を開発した立役者である。
今経済は、かつて体験したことのない危険な領域に入ってしまっています。高学歴の人々がITを駆使し、高度な経済工学理論に基づいた取引を行っていてもこの事態は起きてしまいました。
彼の本には、右上の図が載っています。経済学は後追いでしかないという。
先を走る人は、現場のドロドロした中にタオを発見し「こうやればうまくいきそうだぞ!」という手法を実践に移す(古い脳を活性化させる)。それが、ひらめきであり、直感である。しかし、経営学者は成功者の複数の共通点を抽出し、体系化する(新しい脳を活性化させる)。その中にはタオの痕跡はあるが生々しいタオは肌では感じていない。そして、現在多くの企業が新皮質的な経営をしていることを指摘している。
では、どうしたらいいか?彼は言う。
「燃える集団」作りをすることである。チームが誰にもコントロールされずに、自立的に進むべき方向を決定できる状態にあること。部下を徹底的に受容し、信頼し、自律的な動きにまかせて指示・命令をしないマネジメントスタイルを「長老型マネジメント」と呼んでいる。人間なら誰しも潜在的に持っている、すさまじい能力を引き出し、活用するのである。このような状況下の精神状態のことを「フロー」と彼は呼ぶ。
そして、彼はさらにその理想を以下のように考えている。
1.企業経営の最も大切なことは、まず自分が楽しいこと。次に仲間やお客さんが楽しいこと。人を喜ばせること。本質的に楽しいことだ。
2.意味のない自己満足や優越感、上辺だけのかっこつけ、虚栄心、業界の評判などの見せ掛けの表面的な楽しさと、心の本当の楽しさを混同しないこと。
3.「ちょっとアホ!」に徹して遊び心、いたずら魂を発揮することが大切。
4.「正しいか、正しくないか」「良いかわるいか」「~するべきか、~しないべきか」などの常識的な基準は「ちょっとアホ!」の天敵。
5.自ら賢明に努力し、反省し、根性を持って頑張り、他にもそれを強要することは最悪。いい結果は生まれない。
6.和気あいあいとダラダラ仕事をやったのでは本物の楽しさは得られない。知恵を出し切り、工夫しまくりどんなアホなことでも徹底的に没頭してやりきる。
7.自分に対しても、上司や部下に対しても、お客さんに対しても「正直」であること。
8.社員に理念を徹底しなければいけない。わかりやすく簡単なことばで繰り返し。
9.会社の本当の成長は、規模が大きくなることではない。仲間が楽しく、お客さんが楽しく、会社に関係する人々がより楽しく、なるような会社にすることだ。
10.会社にとって最も大切なことは、社員一人一人の人間的成長。
11.社員の採用基準は、まず「いい奴」かどうか、次に「やってやるで」と思っているかどうか、最後に能力である。
12.「現状分析して、問題を見つけ出し、反省し、解決へ向かう」という従来の仕事の進め方は、あら捜しをして文句をつける拷問を誘う。「楽しくないから反省は一切禁止」「予算管理や目標進捗状況の把握はゲーム感覚で」
13.精密な計数管理をし、詳しく分析して現状把握したところで、やたら忙しくなるばかりで、売り上げが増えるわけではない。むしろ経理処理は徹底的に手を抜いて、昔ながらの「どんぶり勘定」戻せば、社員は暇になり楽しいことを企画するようになる。そのほうが売り上げが上がる。
14.倒産の危機や病気は「気づき」へつながるありがたい出来事だ。
15.学ぶ作業は、知り、納得し、行動し、他人に影響を与えてようやく完結する。
私が組織を纏める方法の、指針としていきたいと思える示唆を多く提供して貰い、一筋の光明が見えた思いのする書物であった。
天外氏の講演会に出られた、現日本サッカー 代表監督の岡田氏のコメントも載せられており、サッカーのチームを創る上でも実践して見たい。


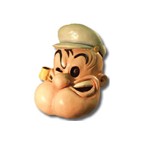
コメント